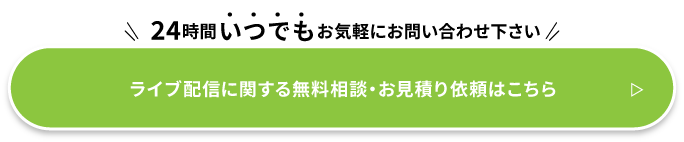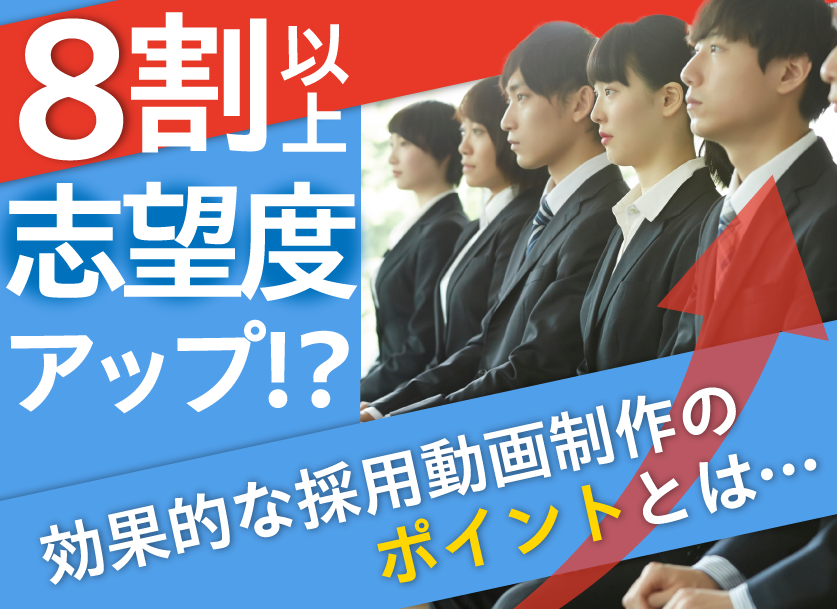ライブ配信委託・代行先を選ぶ前に確認すべき5つのポイントとは?
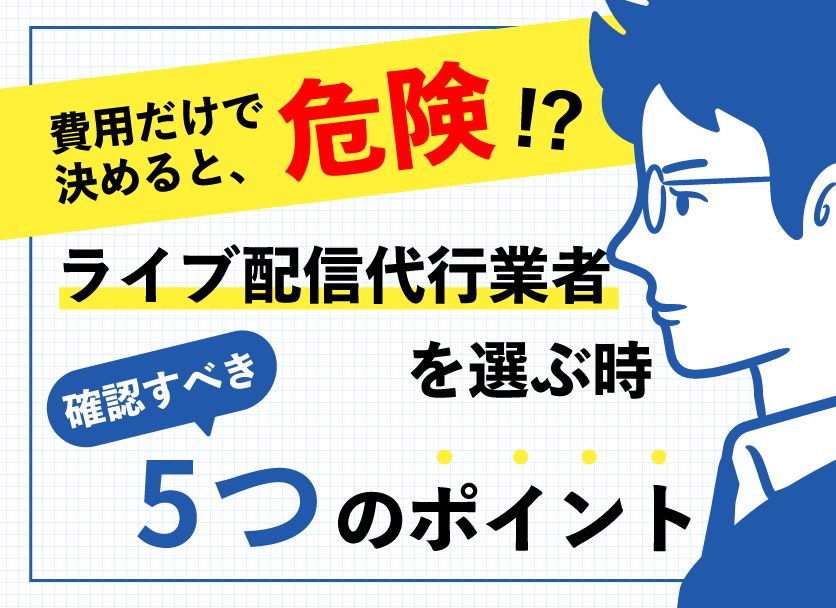
「とりあえず安く済めばいい」…その判断、大丈夫でしょうか?
セミナー・会社説明会・株主総会に至るまで、ライブ配信は当たり前になった今、そして今、「ライブ配信を外注すべきか」「相場はどれぐらいなのか」「いくらが妥当なのか」といった相談が急増しています。
その中で、意外と多いのが「低コストで委託できるところを探しています」 というスタンス。
もちろん、予算は重要です。
でも、費用感だけで選んだ結果「配信中に映像が止まった」「音声トラブルでクレームがきた」なんてことになったら、本末転倒です。
今回は「ライブ配信代行を選ぶときに確認すべき5つのポイント」について紹介いたします。
目次
ポイント1:「何をしてくれるのか」が明確か
見積りには「ライブ配信サポート」と書かれていても、実は業者によって内容はバラバラです。
この為、業務範囲の確認が重要となります。
①配信機材の設営・撤収の有無
「配信機材の設営・撤収作業」は、配信のスムーズな運用を左右する要素です。
プロ仕様の配信には、カメラ・三脚・マイク・ミキサー・配信PC・モニター・ケーブル類など多くの機材が必要であり、正確かつ安全な設営が求められます。
②会場のネット回線チェックの有無
ライブ配信では「安定した上り回線」が命。
ネットワークトラブルが原因で配信が中断した場合、信頼失墜・ライブ配信から離脱・炎上リスクに直結します。
③音響や照明など舞台演出面サポートの有無
視聴者は「配信品質=企業の品質」と捉える傾向があります。
音割れ、マイクの音が聞こえない、照明が暗くて顔が見えない…など、こういったことはすべて“演出ミス”と捉えられるため、見落とすと大きなマイナスポイントになります。
④アーカイブ作成や参加者管理対応の有無
ライブ配信は「その場で終わり」ではなく、アーカイブや参加者管理を通じた“資産化”が重要。
セミナーや社内イベントであれば、配信の再視聴、社内共有による拡散、リード育成に役立ちます。
①~④のような対応がすべて「含まれている」か、「別料金」なのかを把握することで、価格だけでは見えない“本当のコストパフォーマンス”が見えてきます。
ポイント2:「対応範囲と実績」がマッチしているか
ライブ配信には、実は大きく3つのタイプがあります。
①セミナー・説明会型(登壇+資料画面)
登壇者+資料スライドを同時に見せる構成が基本。
一般的に使用される配信プラットフォームは Zoomウェビナー、Microsoft Teams、YouTube Live(限定公開)があります。
主に企業説明会、採用説明会、社内研修、学会発表、IR説明会などで使用されています。
②ハイブリッド型(会場+オンライン)
会場にも参加者がいる一方、オンラインでも同時に配信する形式。
企業の記念式典やフォーラム、カンファレンス。行政・自治体主催イベントなどでも増加中の形態です。
会場(現場)+オンライン視聴の両方を成立させる“二重構成”が求められるので難易度は上がります。
③エンタメ型(音楽ライブやイベント)
音楽ライブや演劇、ダンス発表会など“演出と臨場感”を主役とした配信。
「記録」ではなく「体験の共有」として作り込んでいきます。
ライブ配信ツールは YouTube Live、Vimeo、ニコニコ生放送、独自プレイヤーなど自由度が高いのも特徴です。
ポイント3:「配信トラブル時の対応」が想定されているか
ライブ配信は“機材トラブル・回線落ち・環境音”など、トラブルリスクがつきものです。
万が一の時に「代行業者がどこまで対応してくれるか」は事前に確認しておくことが大事です。
費用の安さを優先して、トラブル時に「何もできませんでした」というのは、大きな信頼損失につながります。
①予備機材やバックアップ回線の用意
ライブ配信は一発勝負。本番中に機材や回線トラブルを起こすと、その瞬間に「視聴不能」「音が途切れる」「映像が止まる」といった致命的な問題が発生します。
この為「カメラ・マイク・スイッチャーなどに予備機材を持ち込んでいるか」「メイン回線とは別に、モバイルルーターやポケットWi-Fiなどのバックアップ回線を確保しているか」「停電や機材熱暴走といった予期せぬリスクに対して代替手段を事前に用意しているか」等を確認しましょう。
②現場で即時対応するスタッフの有無
配信中のトラブルに最速で対応するには、現場に経験豊富な配信スタッフが常駐しているかどうかがカギです。
例えば「カメラ操作・スイッチング・音声調整を担う配信オペレーター」、「登壇者・司会者との調整役となる進行ディレクター」、「ネットワークや機材トラブルに対応するエンジニア」です。
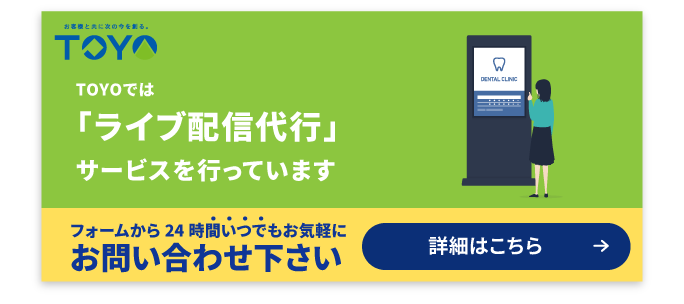
ポイント4:「使用ツールと機材の質」が明示されているか
配信クオリティは、機材と配信ツールの選定次第で大きく変わります。
費用が安くても「スマホで配信」では、プロとしての品質を担保できません。
使っている機材や配信ツールの種類・グレードを確認することで、費用に対する妥当性も判断できます。
①配信ツールは何か
配信プラットフォームの選択は「見せ方」「視聴者体験」「トラブル対応力」などに直結します。
それぞれの特徴を理解したうえで、目的に合ったツールを選ぶ必要があります。
Zoomは「視聴者と対話可能/操作簡易/企業・教育向き」という特徴があり、採用説明会、研修、セミナー、社内会議に選択されます。
YouTube Liveは「高画質・安定性/アーカイブ残しやすい」という特徴があり、一般公開イベント、プロモーション、講演会で選択されます。
Microsoft Teams/独自配信サイトは「ブランド演出やセキュリティ性に優れる」という特徴があり、有料イベント、限定公開型の配信で選択されます。
②カメラは家庭用か、業務用か
カメラの性能が低いと「画質が荒い」「映像が暗い」「ピントが合わない」「動きに弱い」といったクオリティ問題が発生。家庭用と違って業務用カメラは別次元の性能と安定性を備えています。
この為、持ち込むカメラの機種名・スペックの他に、三脚やスライダー、ジンバルなど周辺撮影機材の有無、複数アングル撮影の可否(2カメ以上)等を確認します。
③ 音響機材の種類やマイクの数は十分か
ライブ配信で視聴者が最もストレスを感じるのは“音が聞きづらい”ことです。
映像が多少乱れても見続けられますが、音が悪いと視聴者の離脱率がグッと上がります。
この為「何名分のマイクがあるか?(ワイヤレスマイクの数)」、「同時に複数人が話すケースでも音が混ざらないように調整可能か」、「音のバランス調整するスタッフが常駐できるか」等を確認しましょう。
ポイント5:「サポート体制」に信頼感があるか
最後に大切なのが「人」。
ライブ配信では、現場の空気に即した臨機応変な対応力が不可欠です。「ただの作業員」ではなく「伴走パートナー」になってくれるかどうかで、結果は大きく変わります。
「事前の打ち合わせで内容を理解してくれているか」、「ライブ配信に関する専門的な提案ができるか」、「不安を汲み取って、わかりやすく説明してくれるか」といった部分を確認して良いパートナー選びを進めましょう。
6.ライブ配信代行なら「TOYO」にお任せください!
ライブ配信で重要なのは「安定したネット回線」「高品質な音声」「適切なカメラ構成」「万全なトラブル対応」です。視聴者にとっては“止まらず・聞きやすく・見やすい”ことが最優先。機材・人員・準備の質が成功を左右します。
この為、自社で行うには、機材や経験をもつスタッフ、ある程度の人員を手配する必要があるので、難易度が高いと言えます。
当社では、ライブ配信代行から事後のアーカイブ動画制作やWebサイト関連制作まで行っております。
創業70年以上、お取引企業総数9,800社以上の実績によるプロモーション・マーケティング支援ノウハウによって、安定性と高クオリティなライブ・オンライン配信を実現します。